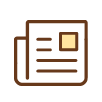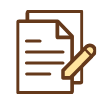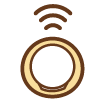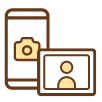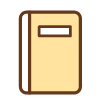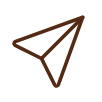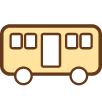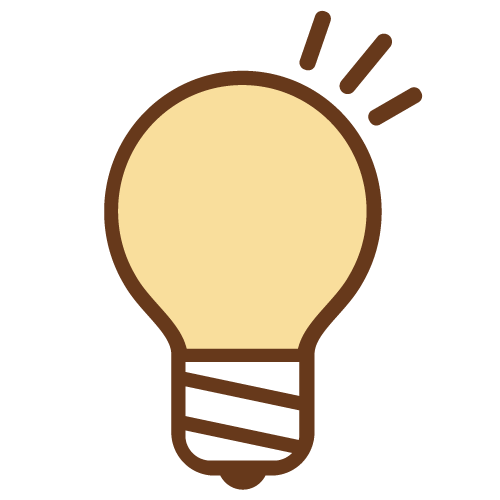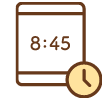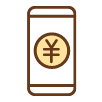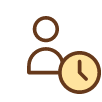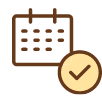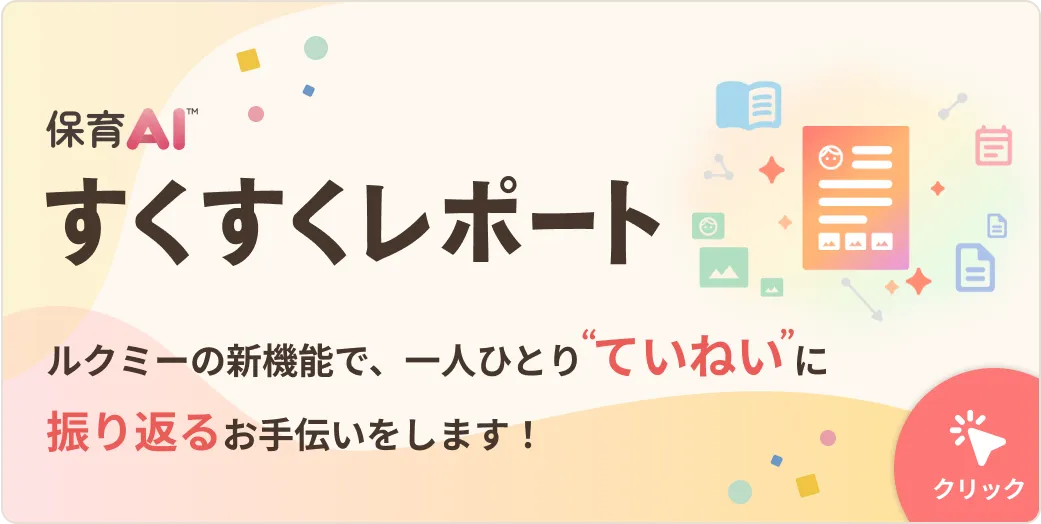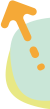保育AIに対する
有識者の声
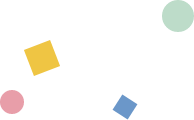
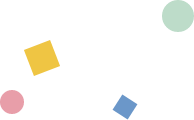
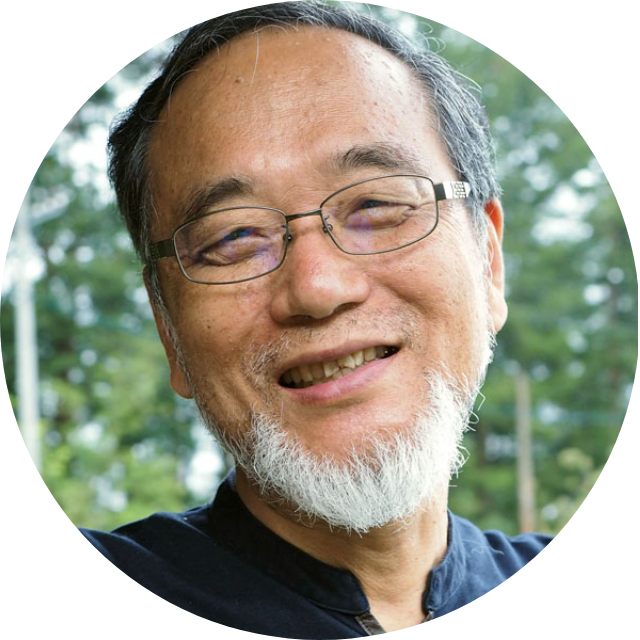
東京大学 名誉教授
AIが得意な分野はどんどん上手に任せて、
人間は保育に時間を使う
人類は、双眼鏡を使って遠くが見えるように 電話を使って遠くの人と話せるように
人間の情報処理機能をテクノロジーで拡張し進化・進歩してきたところがあります。
もっと便利に幸せに暮らしたいと人間が願う限り、AIも必然的に発達していくでしょう。
人間が苦労して記録することでそれなりの効果がある場合を除き、客観的な情報の記録・共有などAIが得意な分野はどんどん上手に任せていって、人間の時間・労力が短縮されれば、人間は保育に時間を使えるわけで、労働を軽減していくことはとても大事だと思っています。
「何のために」をはっきりさせ、
AIを活用したいところを任せていくことが大切です。
いい保育現場は活発に議論しています。
AIが提供してくれる情報を使いながら、アセスメント、リフレクション、対話を支援する。
一人ではなくみんなで議論し合うことが大事になってくるんじゃないかなと思っています。
AIの活用を検討するときには、まずは現状の園の課題を議論して欲しいと思います。
「何のために」をはっきりさせ、AIを活用したいところを任せていくことが大切です。
丁寧であたたかい保育の現場は、AIを上手に活用している。
そのようにして、より信頼される保育になっていくと思います。
今後AIが先生の対話者になるとすれば、
それはとても有効だと思っています。
今の乳幼児の子たちが現在だけではなくて、未来も幸せに生きていくためには、何がこれから大事なのか?
AIというものが私たちの日常生活の中でも、すでにあちこちで登場してきています。
これからの重要なキーワードは「ウェルビーイング」
子どもはもちろん、保育者である先生たち、保護者たちの心と体と環境全部のバランスを保つことが、生涯にまでつながるぐらい重要になってきます。
その点で、ICTを活用して業務負担を軽くすることはもちろん、今後のAI活用にはさらに、子どもがワクワク、先生たちがワクワク、保護者がワクワク、さらに社会のワクワクにまでつながっていけるか、という点がポイントになってくるでしょう。
保育の質を考える際に一番根幹になるのが毎日の振り返りです。
子どもの姿を見ながらの先生自身の心の動き、先生同士でおしゃべりをして、保護者と共有をして分かち合い、明日はこうしようという、先生自身に意欲・パッションが生まれてくることがとっても重要です。
そんなときに、自分が気づかなかったような客観的な視点を出してくれたり、こういうやり方やこういう見せ方とかもあるけどどう?と言ってくれるような、今後AIが先生の対話者になるとすれば、それはとても有効だと思っています。